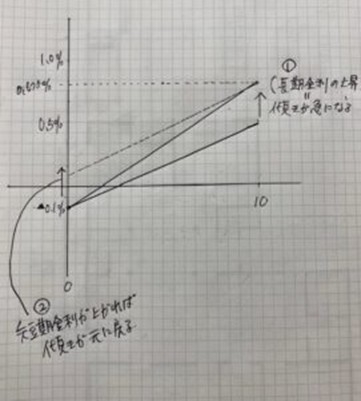【おうちづくりコラム】法律と現実
部屋に必要な採光や換気は
建築基準法に定められている基準に従って計算するのですが、
この基準をクリアしたから充分な採光や換気が取れているのか?
と言うと決してそうではありません。
その多くの窓にはカーテンが設置され、
外から入ってくる光を遮断するからです。
また、カーテンが必要な窓は開けることすら難しいからです。
その上、煩わしい直射光を遮断するために
シャッターまで閉めようものなら
もはや、その窓は窓としての機能を
一切果たさない状態と化してしまいます。
そんなわけで採光と換気に関しては、
決して建築基準法がどうのという話だけで考えるのではなく、
実態レベルで考えなければいけません。
残念なぐらいに薄暗くて空気がどんよりとした
家を建ててしまわないためにも。
この問題を解決するためには、
そもそもカーテンが必要のない窓を
どうすればつくることが出来るのか?
を考えなければいけません。
どのようにすれば、
採光や換気を確保出来ると同時に
プライバシーも守れる窓に出来るか?ということです。

例えば、一般的に窓の高さは
床から2mを天端として
そこから70cm〜90cmの高さの窓を設置することが多いのですが、
この窓の高さは家の中が外から非常によく見える高さであるため
外からの視線が気になりカーテンを設置せざるを得なくなります。
また、リビングをはじめとした南向きの窓に関しては、
南からの直射光を取り入れたいあまりに大きな窓を設置しますが、
窓の向こうに視線を遮断するものがない場合、
外からの視線が気になり、
これまたカーテンを設置せざるを得なくなります。
ゆえ、弊社では床までの大きな窓を設置する場所は、
外からの視線が気にならないところだけに限定しているし、
それ以外の場所の窓に関しても
外からの視線が気にならない高さに設置したり、
外からの視線が気になる場所に設置せざるを得ない場合などは、
透明ガラスではなくフロストガラス(曇ガラス)を使うなど、
視線を防ぐためのカーテンが必要ないように工夫しています。
あ、そうそう。
外の地面の高さは家の中の床の高さよりも約60cm低く、
窓の高さを低くすればするほど外から覗かれやすくなるので、
これも建てる前に知っておいた方がいいかと思います。
そんなわけで窓は1つ1つ立地環境を加味しながら
高さ、形状、ガラスの種類などを丁寧に決めていくわけですが、
これが出来れば予定通りの光が家の中に入ってくるし、
いい気候の時期には心置きなく窓を開けることが出来るし、
開けたままにしておくことも出来ます。
また、プライバシーが担保された透明ガラスからは
外の様子はもちろん、光の動きや四季の移ろい、
そして空を眺めることが出来るので、
圧巻の開放感と贅沢な時間を
感じていただくことも出来ると思います。

いかがでしたか?
快適な家にするために
どれだけ窓が重要な役割を占めているのか
お分かりいただけたのではないでしょうか。
なので、間取りや動線ばかりに気を取られ過ぎず、
窓のことも同じぐらいよく考えながら
設計図をご覧いただけたらと思います。